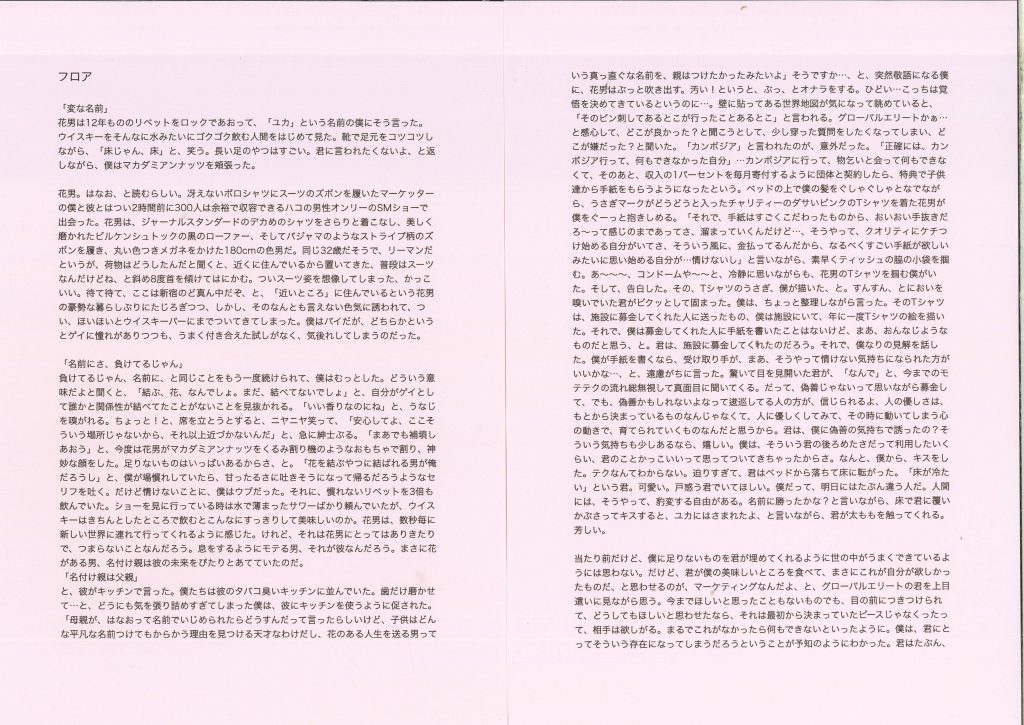星空文庫にも公開していて、チャプターで分かれているのでわかりやすいです。
金藤みなみ「暴動の日」
2040年
生まれた子供をロケットに入れることは、まるで自分が地面から5センチ浮いているような、不安定な気分にさせられた。
ロケット。これに入れれば、子供たちは年金を払わなくていいのだ。生まれたときにこうしてくれていたら、僕だって幸せだったのに。
こういう、親がこういう習い事を教えてくれていたらとか、もっと勉強しやすい環境だったらとか、スポーツに資金をかけることに理解があったらとか、いまだに思うけど、結局、今は、『年金に縛られたこの世界に子供を生んでいいのか』ということで、僕は頭をかきむしることになった。
僕としては、生きられる年齢を縛られた方がよっぽど良いと思って、それを選んだ。
しかし、僕は選んでいたようで、結局のところ、テルに選ばされていたのだろうか。
むしろ、親にその制度を選んでもらえていたら、今まで払ってきて、しかも返ってこない掛け金を、全部取り返せていたという、どうしようもない憎悪を、どうすることもできなかった。
だから、年金から逃げ続ける、30年に縛られた命を、僕は僕たちの子供に保証した.
だけど、その子は、いつか親としての僕を憎むのだろうか。
本当にこれでいいのか、決めていたのに、これから自分自身が死ににいくという時に、今更迷った。
僕は、あと24時間後、ロケットに乗る、つまり、死ぬ。
それまでに、僕たちの狂った日、いや、狂っていなくて正しい日、つまり、暴動の日についてを配信しておきたい。
そのためには、ロケッターについて、暴動の日の主犯についてを話しておかねばならない。
ロケッター(ロケット世代)のこと
年金制度が死んでから、新しく始まったのが、ロケット契約に代表される制度だった。
年金制度自体はなくならず、だんだんと、学生にも、10代にも、納税義務が課せられるようになった。
安楽死が合法化され、腹の底から死にたがる子供が増え、ゆとり世代と言われた30代が未来に失望してこぞって死んだ。
また、安楽死はだいたい70才からというのが(年金が支払われるのがかつては70才だったからか)定説となり、安楽死を自身で保険証に書き込んでおく欄ができた(もちろん、自由意志に任されているが)。だいたいは70才と書き込むことが多かったが、だんだんと、その年齢は下がっていった。
2030年、30〜40代はほとんどいなくなり、50代以上〜100才までと、20代以下だけが残った。僕は20才だった。50才以上は、意識のあるものは20代以下を支援することもあったが、ほとんどは自身の金を身内のための貯蓄にまわした。
そんな時に、「年金を支払わない代わりに、安楽死の年齢を決める」という制度が提示された。
最初、その制度をチラつかせた議員が、八方から糾弾を受け、辞職に追い込まれた。
しかし、だんだんと、年金を収めずとも、「活動的に生きてもらう」ということによる経済効果が無視し難いところまで発揮され、若年層の間で、短い人生を活動的に生きるという方向へブームがやってきていた。
ついに生まれた時から年金の納税義務が発生し、払えない分は、利子付きの借金として扱われることとなった。
未来が見えづらい今日では、安楽死の日が決まっていることによって、年金を支払わなくても済むという制度のディストピア感が、むしろ若年層に支持され、世代別投票で新制度が作られるように、議会は動いた。
詳細が議論され、安楽死希望を40才以下にする人間を中心に消費税・所得税を減免する制度として固まった。また、さらに若く、30才までと年齢を決めていれば、社会効果がより望める大きな挑戦をしてくれる、という意見により、30才までの人生であれば、年金は完全に免除された。東京は、この制度を利用するものに宇宙旅行を保証し、そのうち、契約を結んだ10代を中心に、都庁にあるロケットの模型と共に自撮りをし、配信することが一台ブームとなった。そこから、この新制度を利用する者は、人生を短く華やかに生きる世代として、「ロケッター」と呼ばれるようになった。
この契約を結ぶ権利は、13才未満の親・未成年後見人または13才以上の本人にある。当然、13才になってから、契約を結び直すこともできる。でも、今まで支払っていなかった年金を一気に払うことができない人の方が多いし、分割には利子がつく。その利子を払いきってから、年金がもらえるようになるまでの50代から70代までの間に、まともに働けなくなるものも多かった。
すると、やはり安楽死を選んで、掛け金を取り返し、市場に金をばらまいてもらう、というほうが、社会のためには何かと良いのだった。
テルのこと
言っておくが、僕は「暴動の日」の主犯ではない。
主犯はテルだった。
テルを見たのは、彼のサブチャンネルのサジェストが最初だった。
その頃、ロケット契約は絶対に違法であり、そんなものが実現することは100%あり得ないと、誰もが思っていた。
テルは人生のバランスが偏っていて、息をするように配信に人生の多くの時間を割ける男だった。
編集は緻密で、スッキリ見やすい動画が多かった。
主にゲームと生活についてのチャンネルで、中でも、ただテルが真っ白な部屋で物を捨てていく動画は、ファンからの圧倒的な支持を得ていた。
テルは、激しく聴衆を叱りつけるようなタイプではなく、CGのような滑らかな肌と艶やかな髪をゆらゆらさせながら、ボソボソと喋り、好かれることにてらいがなく、そして、いつの間にかファンが味方につき、ファンとアンチが勝手に戦い始めてしまうような、扇動してしまうような、恐ろしい魅力を持っていた。
僕はゲーム実況のチャンネルを持っていたが、あまり稼働させていなかったが、テルが僕に熱心にコメントをしてくれた。
「君の動画は、普通の感覚を持っていていいですよ!」
と、テルに言われた時は、バカにされているのかと思ったが、それでも、褒められ、認められたことが嬉しかった。
テルが、僕の小さなチャンネルにコメントを書き込むごとに、無数の聴衆がやってきて、わざわざ批判を書き込んで去っていって、ついに僕はチャンネルをやめたが、テルのサブチャンネルの管理を任されることとなった。
その頃、僕は行政書士の仕事にあまり行かなくなっていた。
行ったところで稼いだ金の多くが納税されてしまうのだ。
「それなら働いている場合じゃない」
テルが言うように、僕は思った。
テルは僕と配信なしにでも会うことを好み、自分の父親がロケッターの提唱者だということを告白した。そして、親が安楽死ではなく死んだということも言った。僕は重たいと思った。でも、テルの口調からはその重みは感じられなかった。事実だけが、ずっしりしていて、話し振りはどこまでもツルリとしていて綺麗だった。
年金崩壊から安楽死可決までの間、テルはロケッターになった時のために、着実にバジェットを計算していた。そして、今までの掛け金を取り返してから、彼が飛ぶまでに、デモのファッションを通販し、老人は死ねデモを盛り上がらせ、官邸前で音楽イベントを成功させた。彼のすごいのは、若年層だけではなく、死ねと言われている老人たちにすら支持されていて、DJの中には、70代の者もいたということだ。
テルは言った「みんなの考えが豹変する様子を見るのが楽しいんじゃないか」と。
このデモの終わりには、テルは必ずコンビニの窓を割った。
そして、窓を割るということがなんでもないことのように、学校で問題児が行う、一般的な、普通のことなんだということを、聴衆に刷り込んでいった。
暴動なんて、東京では起きないとずっと言われていた。それが、このカリスマの作ったイベントの、音楽によって、ファッションによって、絵画によって、ダンスによって、パフォーマンスによって、むしろ、一挙手一投足によって、様変わりしてしまった。
僕は、イベントでの物販の手配や、人間が集いすぎて圧死してしまわないように、割れたガラスで怪我をしないように、人数制限と予約管理をしていた。
そのうち、課金の多いファンの予約を優先するようになった。
僕が悩んでいた時に、資金繰りがうまく出来ず、節約がうまく出来て居ないと落ち込んで居た時に、テルは僕に言った。
「いや、みんな、もう、十分節約してる。みんなもう、十分にやっている」
この言葉に、僕は随分救われた。
そうだ、僕らは、もう十分、節約してるし、使いすぎているところは見直しているし、住宅費だってなるべく抑えて、先取り貯金でがんばって、よく、よく、やってきているじゃないか、と。
テルのお姉さんは、テルに「あんた、本当に借金返す気があるのなら、コンビニとかの日雇いバイトでもして、一ヶ月で返せる額でしょう」と言った。
テルは、「あの人、よく、コンビニバイトの人にも、僕にも、差別的なこと思いつけるよね」とせせら笑った。
コンビニで働いている期間、会社の仕事はどうするのか。全額を姉への借金返済に使ったとして、生活費はどうするのか、長期的に続く仕事をやめ、短期でコンビニのアルバイトをし、研修もそこそこに辞めることがばれないように面接を受けろと言うのか、あらゆる点で、テルは正論だった。
テルのファンが議員になり、若年層の納税義務を取り払い、代わりに彼らを安楽死に導いた。安楽死の前に、荒々しく金を使わせた。老人議員たちには、この若者たちの金払いの良さによって、景気が良くなっていく様を、数字で示した。
精子バンクグループや卵子バンクグループのようなものが作られ、テルは真っ先に僕の子供が作られるように、提供者として僕を選んだ。
「君は、ふつーの人代表だから」と、テルは僕の緊張を解きほぐした。
僕の子供が、これから、年金に縛られない世の中に生まれてくる予定だった。
テルは全部うまくやった。親として、自分の子供をロケッターとして自由に生きさせるところまで見せた。僕も当然そうすべきだと思った。
ロケッターは、待機児童にならない。国が保育施設に資金投入したからだ。
ロケッターは、好きな教育が受けられる。お稽古事も、スポーツクラブも、通いたい放題で、むしろ、学校に行くよりも、塾に行くことが奨励された。
その頃、テル自身が議員になっていた。
電車にも定員がある、と言い残して、テルは29才で議員を辞職し、安楽死の日までに、様々なベンチャーに少額投資をしはじめた。僕は28才で、いまだに彼の秘書みたいなことをしていた。自分のチャンネルは、もう動かさなくなっていた。
安楽死の期日は自分で決めることが出来るが、暗に他人によって決められてしまうことを、大きな権力によって決められてしまうことを、「トランスファ(転送)」なんていうようになっていた。権力は、宗教であることもあるし、親であることもあった。
テルは、チャンネルの視聴者たちに、自分をトランスファしてもらうことを選んだ。
そして、彼が主犯となる、あの日を迎えることになる。
センヨウさんのこと
あの日について語る前に、センヨウさんのことについても触れておこう。
センヨウさんは、一緒に秘書をしていたが、ちょっと意地悪だなと思うことが多かった。違法というほどひどいことをされるわけではないが、予約のミスをすると、「あなただけができていない、他の人はみんなできている」とネチネチと言い、そのくせ、自分はかなりサボる方だった。
配信中の自動文字起こしを、調整する仕事を、「日報」と言っていたが、日報を良くサボった。
二人で組むと、仕事のしわ寄せが自分にきてしまうのだ。
秘書グループの全員にセンヨウさんは嫌われていたので、僕としてはやりやすかったが、センヨウさんと僕の出社日には気が滅入った。
『ひどすぎるね。センヨウさんは病気なんじゃないかと話しています。ごめんね、はやく新しい人材を確保できるように考える』と、テルは言ってくれた。僕は、はやくセンヨウさんをなんとかしないと、みんなが不幸になってしまうと思った。人の不幸を祈るなんて、私は、結局じぶんにかえってきてしまうから、そんなことできないと思っていたけど、でも、みんなが狂って、混乱してしまう。やっぱりセンヨウさん、の命は、『トランスファ(転送)』するべきだった。トランスファなんて、殺人のことを、次の世界に飛ばす、といったような、ファンタジーでまとめなければ、僕らは心を保っていられなかった。
結局センヨウさんは仕事を辞め、そのあとのことは知らない。
暴動の日
暴動の日になった。
エモーショナルな配信が、そこら中で行われ、言葉が紡がれ、歌われた。
この日は、物語として、あらゆるチャンネルで消費された。
テルの信者が、僕に近づいてきて、自分が生まれてきて本当によかったと言った。
みんな、テルがデザインしたジャケットを着ていた。
ネイビーの細めのストライプのデザインがあしらわれた丸襟、キュートなパフスリーブ、金のボタン、白いスカートのようなズボン、こちらも縦にストライプ、そして、蛍光に光るビニールタイプのイエローベスト。
イエローベストは、フランスの暴動に触発されているものの、イエローであればなんでもよいとされていた。
けれど、やはり、テルのデザインした、ゆったりとしたユニセックスなベストが一番売れた。
サコッシュやビニールでスケルトンタイプのイエローのカバンも流行っていた。
暴動の中心にテルが立ち、号外を配った。
視聴者たちの中で、長い議論があったあげく、トランスファは取り下げられ、テルは長く生かされることになっていた。
テル(たち)が半年ほどかけて割り続けた街中の窓ガラスで足を怪我しないように、ゴツめの黒い安全靴が流行っていた。
最初はコンビニのガラスが割られても、すぐに復旧していたが、そのうち、割られたコンビニの店員たちが味方し、コンビニの中のありとあらゆるガラスが割られ始めた。
そして、街へとガラス割りが広がり、占拠したエリアの入り口で、テルはさながら検問のようなことをやり始めた。
テルが官邸前で火を放ち、周りで乱闘が起き、何人かの犠牲が出ている間、マイクを手にとって言った。
「俺たちは怒っている。俺たちは増税に怒ってる。俺たちが暴動を起こさないと思ったか?『みんながやっている』を作れば、俺たちは暴動を起こすぞ。簡単なことなんだ。俺たちはそう言う風に生まれついているからな。むしろわかりやすいスイッチで助かったよ。なあ、わかってるのか、返せよ、満額で返せよ、俺たちを返せ、貸してるもの返せって言ってるだけだよ、自由を返せ」
聴衆が完成をあげ、乱闘が続き、泣くものが続出し、突然、背後から小柄な若者がダンプのような勢いでやってきて、テルを刺した。
テルは抵抗した。
しかし、そいつはなんども何度もテルを刺し、刺しながら、「ありがとう!ありがとう!」と叫んでいた。
多くの大人に若者は取り押さえられた。
暴動の日は、テルがかつて安楽死を決めていた日だった。
テルの死を、僕は前後不覚のまま、泣き叫びながら、世界に配信した。
テルに、おい、おい、と声をかけていた。
みんなが灯油タンクを手にしていた。
「このままやろう」と、テルは言った。
自分が決めたことを覆さない、ということに、テルは誇りをもっていた。
テルに、代わりに僕が全部やれ、と言われた。
僕にはできないと思った。
テルは、小声で、痛いとか、グロいとか呻きながら、最後に、「君はすごいよ、ちゃんと会計やってさ、子供に未来を与えてさ、普通を生きてるよ、普通はすごいことだよ」とか、そういったことを、「痛い」と血混じりに呟いて、「俺たちの子供達をさ、ロケッターにしてくれてさ、ありがとうな、ほんと、それさ、普通だよ、すごいよ、繋がってるよ、ありがとう」と弱々しく呻いて、事切れた。
勘弁して欲しかった。
テルが言うことに逆らうことは、僕には絶対に出来ないのに。
僕は、テルの握っていたマイクを奪って、跪(ひざまず)いたまま、「死ね!みんな死ね!」と叫んだ。
思ったよりも落ち着いたトーンだった。
テルの頭は重く、腕は軽く、何もかもが信じられなかった。
手が痺れていた。
「返せ!俺たちの人生を返せ!年金返せ!卑怯な奴らめ、返せ!」と、ゆっくり、ゆっくり叫んだ。
どこか、違う人間が言っている言葉を聞くような気持ちだった。
全て、テルが言っていた言葉だった。
僕は凡庸だった。
みながエモーショナルな表情を浮かべ、高揚し、僕を肯定した。
「産まない、産まないことで守ってやる、産む、産んでも借金にがんじがらめにならないように、命の長さを決めて、税金から逃れさせてやる」ぐるぐると、どうどう巡りのことにとらわれて、僕は動けなかった。
僕の子供は、もう保育器の中にいて、ロケッターの手続きを、すでに行なっていた。
本当に、僕は、何かを動かすような力を持っていなかった。
みんながテルを肯定する。
足元のガラスの破片が光って、跪く僕の顔を映した。
僕はテルの顔になっていた。
ロケットへ
そして今の時間に戻る。
僕は、もう動画を撮らなくても良いのに、目の前に広がる光景の字幕やカット割りのことを考えていた。
ロケットの中に、薄い霧が出始めていた。
僕の腕に、管が入り、血管は、ぽつぽつと、薬を受け入れていた。
手厚い保証が約束され、教育された子供達は、実に強くたくましく、様々な事業で成功を収めた。
僕は資金繰りに奔走することもなくなり、財団を作り、さらに手厚い福祉を未来の子供達に約束した。
命が制限されているから、僕は馬力を出せたのだと思っていた。
しかし、いまわの淵に、こう思った。
「僕はまだ本気になれていなかったんじゃないか?」と。
走馬灯のこと
僕は急に後悔し始めた。
息子を保育器の外から見たことを思い出した。
息子は大きく息をしていた。
彼の肌はざらついていた。
つぶれそうな指だった。
風船のようだ。
そして、はちきれそうだった。はちきれるのは僕のほうだった。
薬が効いてきて、30年が終わろうとしていた。
安楽死を「選んだ」日から、30年というように、日付を変えた方がいいんじゃないだろうか、制度がおかしかったんじゃないかと思い始めた
目の前の金ばかり追いかけちゃダメだよとしたり顔で言ってくる投資家の友人の顔が浮かんだ。
彼らはうるさかった。
幸福なロケッターたちが、未来のために、十分に保障を受け、教育を受けさせてもらえることを思い、僕も幸せな気持ちになった
しかし、僕の中で、僕が反論した
「なぜ、ロケッターが優先されるんだ?」と。
「全ての子供達に教育を保証しろよ」と、僕が怒った。
一体誰に?
犠牲になるのは、みんな子供達だった。
そんな子供達に、お前たちは30歳で死んでこい、と、僕は言ったのだ。
僕が、テルに反抗することなんて、恐ろしくて出来なかったから。
テルがこの世にいなくなっていても、僕は僕に反抗することなんて、出来なかった。
怖かったから、全部を制度のせいにして、僕の言うことを聞く、良い子の、ロケッターに手厚い福祉と教育を保証し、言うことを聞かない、悪い子たちに、重税を課し、まるでそれが真の平等であるようにした。
怖くて逃げ回って、自分には権力なんてないと信じきっていた。
圧政だったり、ひどい制度というのは、ひどい思考の末に行われるものだと思っていた。
テルに「普通だ」と言い聞かせられてきた臆病な「僕」みたいな人間が、圧政を行ってしまった。
止めなければ、と、取り返しのつかないことを巻き戻したい気持ちが襲ってきて、耐えられず、僕は煙の中でもがいた。
僕は気が狂ったのかもしれない。
「返せ!」と叫んだ自分の声がロケットの中で揺れ、窓を開けようとした。
30年の終わり
開けようとした窓が、外側から空いた。
センヨウさんが、僕のロケットを開けたのだった。
最初、光と空気に満たされ、眩しくて目が潰れるようだった。
目を反射的に閉じている間、センヨウさんは僕に話しかけた。
妄想か幻覚か、センヨウさんが本当に存在しているのか、僕にはもうわからなかった。
くたびれた声だった。
彼は宇宙研究を始めていた。
新しい街を作るから、手伝って欲しいと言われた。
宇宙にいけば、きっと開けていて、自然で、定員なんて無いと思いたかったけど、宇宙には絶対に定員がある、と、僕は僕の中で思った。
僕は、「新しさ」に、なんの希望も持てないでいた。
閉じ込められていた瞬間まで、僕は制度を変えなければともがいたのに、いざ蓋を開けられるとすくんだ。
センヨウさんが蓋を開け、四角く切り取られた世界は、あまりに、あまりに眩しくて、淀みきっていたロケットの中の空気を2秒で入れ替え、僕の中に、情けなくも、希望のようなものが湧いてきてしまった。
僕は泣いた。
自分の空気の入れ替えのために、かりそめの新しさのために、僕はあらゆる人を騙したような気分になった。
借金のない、稼いだお金を全部自分で使うことが出来るためなら、僕はなんだってしたかったはずだった。
肺が圧迫された。
僕の胸の上に、息子が入ったロケットが乗っていた。
番号が、息子のものであることが、手で触って確かめてわかった。
驚き、持ち上げようとしたら、手に力が入らず、ロケットに胸毛がへばりつき、またストンと胸の上に戻り、小さなロケットのドアが開いた。
息子は中にはいなかった。
「保育室です」
と、センヨウさんが告げた。
無数の後悔に襲われ、僕は「情けないけど、息子に恨まれるのが怖いんだ」と返した。
今すぐ死なせてほしかった。
「ど、どうやって入ったんですか」と、センヨウさんに聞くと、
「正面から、開けたいので開けさせてくださいって言ったら開けさせてくれました。」とそっけなく返される。「みんな、外部からのお願いには、もう反抗する気力が無いんでしょう」
センヨウさんは続けた。
「まだ、彼は、あなたの息子さんは、社会に出てませんからね。まだなにが好きなのかも、なにが苦手なのかも、どんな風にものごと受け止めるかも、未知数ですよ。そんな赤ん坊は、まだ人間じゃないですよ。息はしてますけど、何を思っているかはわからないです。」と言って、急に涙を流した。
「私は、社会の仕組みは理解しているだけなんです、子供が生まれてこなければ、子供は辛い思いをしなくて、借金をしなくて良いんです。でも、私は理解しているだけで、一つ一つの生活と世界が繋がっているってことを、本当に理解してはないんです。子供は、まだ人間じゃなくて、何を思うか、何を背負わされると嫌で、何を安心だと感じるか、腹がたつのか、どのように自由を捉えるか、まだ、決まってないんです。せいぜい快か不快かくらいしかないんです。まだ、あなたは憎まれてないんです。」
逆光で、センヨウさんの顔が、ぐにゃぐにゃになって、テルの顔に見え、僕は目を見開いた。
「これから憎まれるんです。」
僕のひたいの上に、センヨウさんの、テルの、涙と、鼻水が、ぼたぼた落ちた。
「あと、恨まれたくないなら洗脳したらいいんじゃないですか」と、センヨウさんの真面目な顔に戻って言った。
僕は泣いた。
どこに、正解があったんだろうか。
どこに、ずるく無い明日が、子供に保証できる未来があったんだろうか。
僕はそれを、見逃して、気づいたら手放してしまっていたのだろうか。
自分が決めたことを覆さない、ということに、テルは誇りをもっていた。
僕はテルと全然違った。
僕は、自分が決めたことを覆す道を選んだ。
センヨウさんは、フラフラでつまようじみたいな僕の腕を抜けるかと思うほど引っ張ったので、僕はロケットから出る。
新しい光ばかりではないはずの新しい街に引っ越すために、文句を言われながら、文句を言い、自分の権利を主張し、僕が奪ってきた命の制度を食い止めるために、今度こそ、僕自身を裏切らないために。


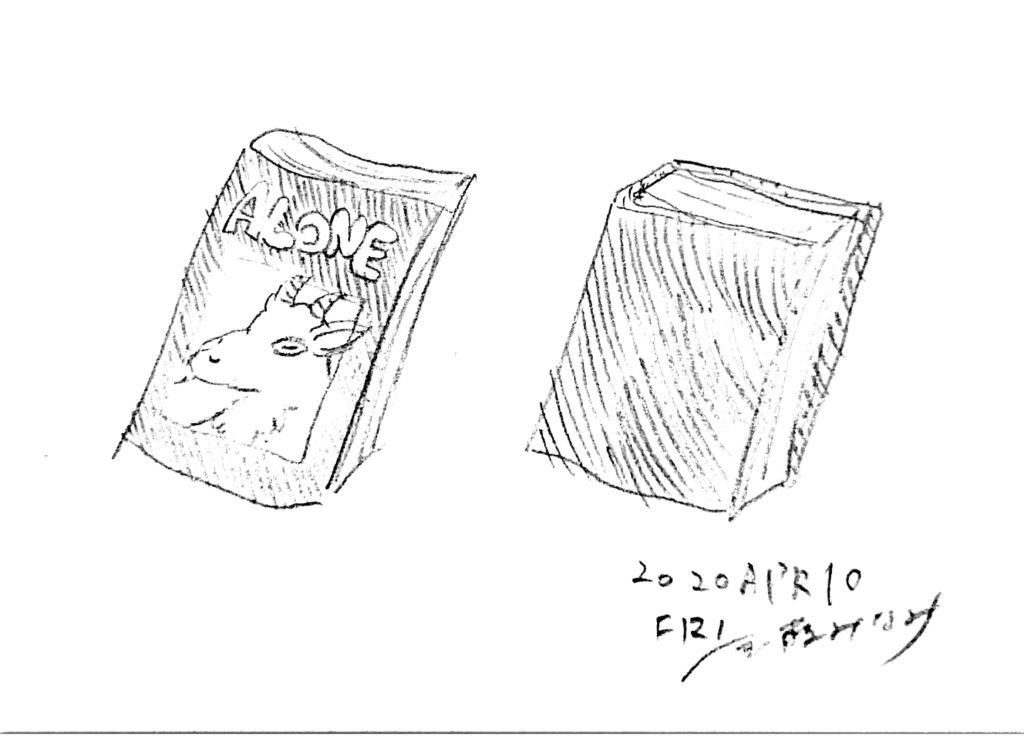
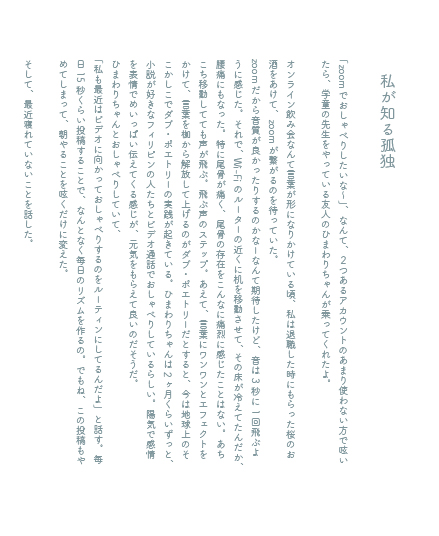
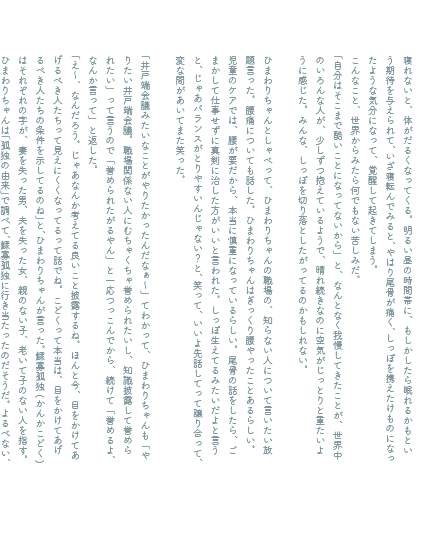





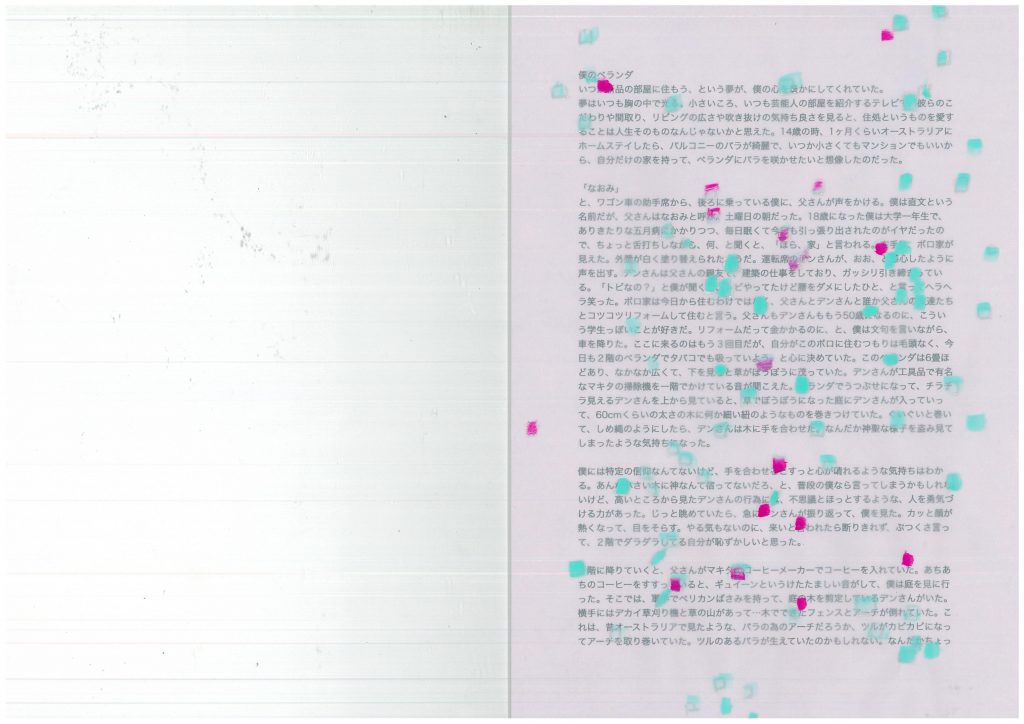
 フロア
フロア