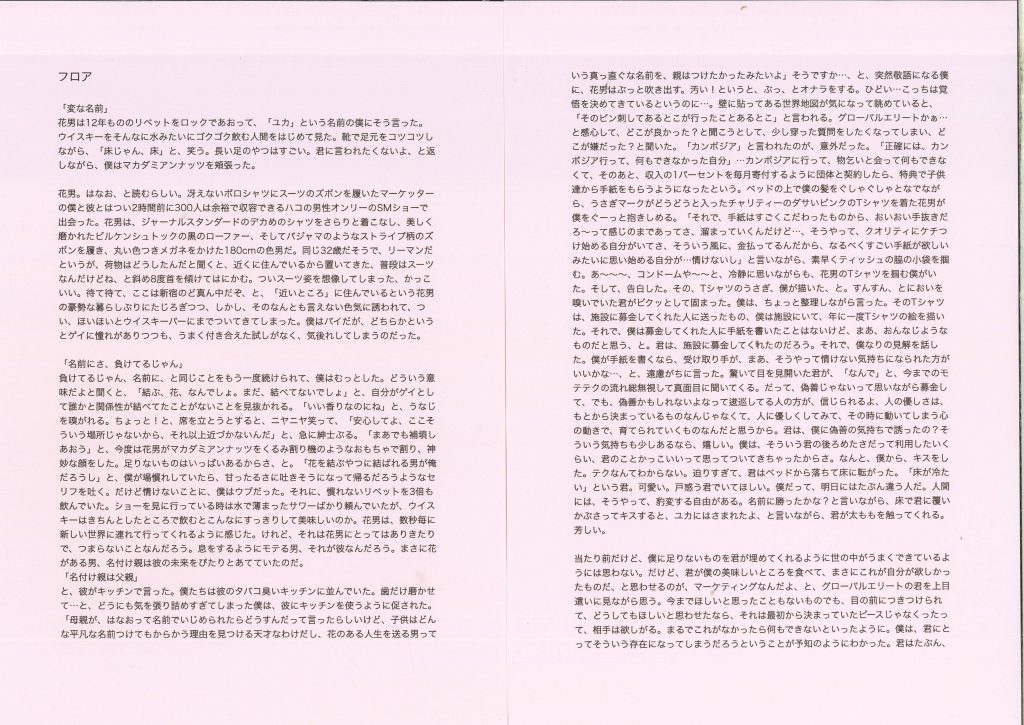フロア
フロア
「変な名前」
花男は12年もののリベットをロックであおって、「ユカ」という名前の僕にそう言った。ウイスキーをそんなに水みたいにゴクゴク飲む人間をはじめて見た。靴で足元をコツコツしながら、「床じゃん、床」と、笑う。長い足のやつはすごい。君に言われたくないよ、と返しながら、僕はマカダミアンナッツを頬張った。
.
.
.
.
.
花男。はなお、と読むらしい。冴えないポロシャツにスーツのズボンを履いたマーケッターの僕と彼とはつい2時間前に300人は余裕で収容できるハコの男性オンリーのSMショーで出会った。花男は、ジャーナルスタンダードのデカめのシャツをさらりと着こなし、美しく磨かれたビルケンシュトックの黒のローファー、そしてパジャマのようなストライプ柄のズボンを履き、丸い色つきメガネをかけた180cmの色男だ。同じ32歳だそうで、リーマンだというが、荷物はどうしたんだと聞くと、近くに住んでいるから置いてきた、普段はスーツなんだけどね、と斜め8度首を傾けてはにかむ。ついスーツ姿を想像してしまった、かっこいい。待て待て、ここは新宿のど真ん中だぞ、と、「近いところ」に住んでいるという花男の豪勢な暮らしぶりにたじろぎつつ、しかし、そのなんとも言えない色気に誘われて、つい、ほいほいとウイスキーバーにまでついてきてしまった。僕はバイだが、どちらかというと憧れがありつつも、うまく人と付き合えた試しがなく、気後れしてしまうのだった。
.
.
.
.
「名前にさ、負けてるじゃん」
負けてるじゃん、名前に、と同じことをもう一度続けられて、僕はむっとした。どういう意味だよと聞くと、「結ぶ、花、なんでしょ。まだ、結べてないでしょ」と、自分がゲイとして誰かと関係性が結べてたことがないことを見抜かれる。「いい香りなのにね」と、うなじを嗅がれる。ちょっと!と、席を立とうとすると、ニヤニヤ笑って、「安心してよ、ここそういう場所じゃないから、それ以上近づかないんだ」と、急に紳士ぶる。「まあでも補填しあおう」と、今度は花男がマカダミアンナッツをくるみ割り機のようなおもちゃで割り、神妙な顔をした。足りないものはいっぱいあるからさ、と。「花を結ぶやつに結ばれる男が俺だろうし」と、僕が場慣れしていたら、甘ったるさに吐きそうになって帰るだろうようなセリフを吐く。だけど情けないことに、僕はウブだった。それに、慣れないリベットを3倍も飲んでいた。ショーを見に行っている時は水で薄まったサワーばかり頼んでいたが、ウイスキーはきちんとしたところで飲むとこんなにすっきりして美味しいのか。花男は、数秒毎に新しい世界に連れて行ってくれるように感じた。けれど、それは花男にとってはありきたりで、つまらないことなんだろう。息をするようにモテる男、それが彼なんだろう。まさに花がある男、名付け親は彼の未来をぴたりとあてていたのだ。
.
.
.
.
「名付け親は父親」
と、彼がキッチンで言った。僕たちは彼のタバコ臭いキッチンに並んでいた。歯だけ磨かせて…と、どうにも気を張り詰めすぎてしまった僕は、彼にキッチンを使うように促された。「母親が、はなおって名前でいじめられたらどうすんだって言ったらしいけど、子供はどんな平凡な名前つけてもからかう理由を見つける天才なわけだし、花のある人生を送る男っていう真っ直ぐな名前を、親はつけたかったみたいよ」そうですか…、と、突然敬語になる僕に、花男はぶっと吹き出す。汚い!というと、ぶっ、とオナラをする。ひどい…こっちは覚悟を決めてきているというのに…。壁に貼ってある世界地図が気になって眺めていると、「そのピン刺してあるとこが行ったことあるとこ」と言われる。グローバルエリートかぁ…と感心して、どこが良かった?と聞こうとして、少し穿った質問をしたくなってしまい、どこが嫌だった?と聞いた。「カンボジア」と言われたのが、意外だった。「正確には、カンボジア行って、何もできなかった自分」…カンボジアに行って、物乞いと会って何もできなくて、そのあと、収入の1パーセントを毎月寄付するように団体と契約したら、特典で子供達から手紙をもらうようになったという。ベッドの上で僕の髪をぐしゃぐしゃとなでながら、うさぎマークがどうどうと入ったチャリティーのダサいピンクのTシャツを着た花男が僕をぐーっと抱きしめる。「それで、手紙はすごくこだわったものから、おいおい手抜きだろ~って感じのまであってさ、溜まっていくんだけど…、そうやって、クオリティにケチつけ始める自分がいてさ、そういう風に、金払ってるんだから、なるべくすごい手紙が欲しいみたいに思い始める自分が…情けないし」と言いながら、素早くティッシュの脇の小袋を掴む。あ~~~、コンドームや~~と、冷静に思いながらも、花男のTシャツを掴む僕がいた。そして、告白した。その、Tシャツのうさぎ、僕が描いた、と。すんすん、とにおいを嗅いでいた君がビクッとして固まった。僕は、ちょっと整理しながら言った。そのTシャツは、施設に募金してくれた人に送ったもの、僕は施設にいて、年に一度Tシャツの絵を描いた。それで、僕は募金してくれた人に手紙を書いたことはないけど、まあ、おんなじようなものだと思う、と。君は、施設に募金してくれたのだろう。それで、僕なりの見解を話した。僕が手紙を書くなら、受け取り手が、まあ、そうやって情けない気持ちになられた方がいいかな…、と、遠慮がちに言った。驚いて目を見開いた君が、「なんで」と、今までのモテテクの流れ総無視して真面目に聞いてくる。だって、偽善じゃないって思いながら募金して、でも、偽善かもしれないよなって逡巡してる人の方が、信じられるよ、人の優しさは、もとから決まっているものなんじゃなくて、人に優しくしてみて、その時に動いてしまう心の動きで、育てられていくものなんだと思うから。君は、僕に偽善の気持ちで誘ったの?そういう気持ちも少しあるなら、嬉しい。僕は、そういう君の後ろめたさだって利用したいくらい、君のことかっこいいって思ってついてきちゃったからさ。なんと、僕から、キスをした。テクなんてわからない。迫りすぎて、君はベッドから落ちて床に転がった。「床が冷たい」という君。可愛い。戸惑う君でいてほしい。僕だって、明日にはたぶん違う人だ。人間には、そうやって、豹変する自由がある。名前に勝ったかな?と言いながら、床で君に覆いかぶさってキスすると、ユカにはさまれたよ、と言いながら、君が太ももを触ってくれる。芳しい。
.
.
.
.
当たり前だけど、僕に足りないものを君が埋めてくれるように世の中がうまくできているようには思わない。だけど、君が僕の美味しいところを食べて、まさにこれが自分が欲しかったものだ、と思わせるのが、マーケティングなんだよ、と、グローバルエリートの君を上目遣いに見ながら思う。今までほしいと思ったこともないものでも、目の前につきつけられて、どうしてもほしいと思わせたなら、それは最初から決まっていたピースじゃなくったって、相手は欲しがる。まるでこれがなかったら何もできないといったように。僕は、君にとってそういう存在になってしまうだろうということが予知のようにわかった。君はたぶん、一夜、遊んだり、あるいは、経験のない僕をかわいそうだと思って、部屋に連れて行って添い寝できれば上出来で、いい思い出を作ってあげようとでもいう偽善だったかもしれないけど。ちなみに、僕の話したこと本当だと思う?と、ちょっと笑いながら聞いた。「うっそ…」と、君が青ざめる。本当だよ、君をちょっと違った君にするのが、僕の役目さ。
.
.
.
.
たぶん、僕がうまく君を誘惑できたと思った部分は、まったく君には届いていないだろう。そして、君が僕に使ったテクも、僕にはほとんど効いていない。人は、自分が相手を落とせたと思っている魅力以外のところでこぼれ落ちた香りを捕まえて、人を好きになるのだろう。僕は君と始まるたどたどしい関係を予感して、でも、明日には会えなくてもいいという刹那的な気持ちになりながら、やっぱり花を結ぶのが僕の役目だったな、と、名前の不思議な役割に思いをはせる。
.
なんたって、フローリングに寝そべる君は花のように良かったのだから。
(初出:2017.08 「便箋BL」)